漱石の有名な青春小説。平凡な小説のようで平凡じゃない。美しい情景描写と魅力的な登場人物が織りなす人間模様。唯一無二の世界観。私が純文学へ興味を持つきっかけとなった小説です。物語を通じて、何も起きなかったようでそれぞれの登場人物の心に残る形のない何か。三四郎という自分に容易に置き換えられそうな、感情移入しやすい主人公を通じて、読者も物語に入り込みその“何か”を共有できる、小説を読む楽しさを教えてくれる原点のような作品です。
真面目で優しい九州男児
三四郎は大学進学のために地元の九州から東京に上京する電車の中で一人の女性に出逢います。名古屋で一旦宿をとる際、三四郎は女性から自分一人だと不安だから宿を案内してほしいと無理に頼まれます。そして断れないうちに同じ部屋に泊まることになってしまいます。
お風呂上がり、一つの蒲団。三四郎のピンチです 笑
そこで三四郎は“ノミ除け”と称してシーツをぐるぐる巻いて女性との間に仕切りを作って寝ました。女性とは一言も話しません。そして次の日の朝、別れ際に女性から「度胸のない人」と嘲笑されます。
三四郎、かわいそう!悪くないです。三四郎の真面目な人柄がよくわかるエピソードです。そしてこれは、これから都会でとんでもない女性に振り回されるという伏線でしょうか。がんばれ三四郎。
美禰子との出会い
三四郎が美禰子と初めて会う有名な場面。美禰子という存在に三四郎が強く惹きつけられる、まるで息を呑むように釘付けになっていく、スローモーションのような時間の流れの描写が見事です。黒眼の動き、まるで心を見透かされているような底知れぬ恐ろしさ。でも目を逸らせない、探していたものを“見つけてしまった”ような感覚。美禰子とすれ違うまでのわずかな時間。二人の出会いの描写が見事です。
そして、大学が始まったのに学生どころか先生も来なくてなかなか授業が始まらないのに笑いました。誰もいない教室に真面目に通っていた三四郎が癇癪を起こして出ていくのも面白いです。机にある素人とは思えない凝った彫刻、先生の似顔絵を必死にかいている隣の人。三四郎、青春してるなぁと思いました。ちなみにこの先生の似顔絵をかいていた人は、のちに三四郎の友達となる佐々木与次郎です。いいキャラしてます 笑。三四郎との絡みが面白いです。
美禰子という女性
三四郎に見られていることを意識して夏のさかりに椎の実がなっていないか人に聞いたり、おそらく尋ねなくても問題なさそうな病室の場所をわざと三四郎に尋ねたりする。三四郎が自分に見惚れていることをわかってにっこりと笑ったり。そして髪には野々宮さんからもらったリボン。美禰子、確信犯です 笑。これは三四郎は敵いませんね。 防御もできずにノックアウトです。
でも決して媚びたりせずに落ち着いていて、凛として芯のある女性です。
でもかわいらしい時もあります。広田先生の引っ越しの時に、与次郎、三四郎、美禰子で3人でわちゃわちゃ手伝っている場面があるのですが、ここのやりとりが3人ともかわいい!ほっこりします。そしてこの時の澄んだ空気と青空、雲、心地よい風。落ち葉。秋の晴れた清々しい良い1日がその時の温度まで肌で感じられるような描写が見事です。これから何かが始まりそうなワクワクとした胸騒ぎと秋の爽やか且つ少し切ない雰囲気がシンクロしています。特に“女は秋の中に立っている”という描写がおしゃれです。この詩的な表現は素敵すぎる!
そしてこの辺りから三四郎が美禰子にメロメロになっていきます。こんなに態度に出ていたらみんなそのうち気づくよ?途中で野々宮さんが合流すると静かに警戒しだす三四郎、ちょっと落ち着いて 笑
迷える子(ストレイ シープ)
菊人形をみんなで見に行って2人ではぐれた時、三四郎と美禰子はとある川縁に座って話をします。最初はぎこちなかった三四郎と美禰子が、互いに変な遠慮をせずに少しずつ打ち解けていく様子が描かれています。広田先生や野々宮さんが自分たちを探しているだろうことを気にする三四郎と、気に留める様子のない美禰子。自分たちは大きないい年をした迷子だから大丈夫だと。そこで三四郎に「迷子」の英訳を知っているか尋ねます。
“迷える子 ストレイ シープ”
小説の中で重要なキーワードである有名な“ストレイ シープ”ですが、これを美禰子は何のために、どういった意図を持って三四郎に言ったのでしょうか。色んな意見があると思いますが、美禰子という女性を理解する上でとても重要なキーワードだと思いました。そして少なくとも、美禰子は野々宮さんではなく三四郎にこの言葉を言った、というところに美禰子の狡猾さと甘えがあるように思います。
運動会の帰り道、三四郎の前で野々宮さんを褒める美禰子。後日の広田先生の“優美な露悪家”という言葉が三四郎に刺さります。美禰子の目的は?三四郎の自惚を成敗しているつもりなのでしょうか…?
また二人で原口さんからもらった招待券で展覧会展に行ったとき、三四郎がちょっと天然なところを発揮する場面があります。顔を見合わせて笑う二人。素直でまっすぐな三四郎の心の美しさに美禰子は惹かれていたのではないでしょうか。でも美禰子は天性の魔性の女ですね。可哀想なくらい三四郎は振り回されています。
ヘリオトロープの香り
三四郎と美禰子は偶然街で居合わせます。よし子と香水を買いに来ていた美禰子は三四郎に買う香水の相談をします。香水なんて全くわからない三四郎。三四郎が適当に選んだ香水を言われるままに買う美禰子。三四郎はちょっと気の毒になります 笑。美禰子が買ったこのヘリオトロープの香水は物語の最後に重要な意味を持ちます。二人を結びつける香りです。ちなみに私はこのヘリオトロープの香りをかいでみたくてヘリオトロープを育てたことがありますが、花の香りを嗅ぐ前に枯らしました 笑。また機会があったら育ててみたいです。
そして三四郎は美禰子の結婚が決まったことをよし子から聞きます。おそらく最後となる美禰子に会うために教会で美禰子を待つ三四郎。
美禰子の白いハンカチから香るヘリオトロープの鋭い香り。
“四丁目の夕暮れ。迷羊。”
自分の罪を自覚する美禰子。
そして二人は分かれます。
まるで映画のワンシーンのようです。淡々とした描写が余計に切なさを引き立てます。肌身離さずにヘリオトロープを染み込ませたハンカチを持っていた美禰子。この日三四郎が会いに来ることも知らなかったと思います。
美禰子とは何だったのか。三四郎を惑わした罪を自覚はしているものの、本当にそれだけだったのか…?美禰子の心理描写が一切ないので謎のままです。それがこの小説を味わい深くしています。
美禰子が欲しかったものとは
三四郎のことを本当はどう思っていたのか。ただ心を弄んで楽しんでいただけだったのか。彼女が“欲しかったもの”とは何だったのか。
美禰子が欲しかったものは良い職業に就いた立派な男性と結婚して得られる安定した未来?
ハイスペックな男性の奥さま、なんて相手にとっては別に自分じゃなくてもいい。この縁談話が最初はよし子に来た話であったように、その代わりはおそらくいくらでもいる。
彼女が本当に欲しかったものは、“自分じゃないとイヤだ”と言ってくれる存在だったのでは?誰かにとって絶対的な存在となって、自立した新しい時代の女性になりたかったのでは?
きっと野々宮は最終的に彼女ではなく自分のこと(研究)を優先する。でも三四郎は違う。
駆け引きもせず、自分をひたすらに追ってくれる三四郎みたいな誰かを本当は求めていたのでは?でも兄、世間体、置かれた自分の立場。この時代に三四郎の手を取ることはできない。自分でもそれが自分にとって一番幸せだとは思っていない。
二人で迷羊になることはできない。
許されるその時まで自分を追ってくれる三四郎との時間を過ごしたかったのでは?ちょっと三四郎のこと好きだったよね?じゃなきゃ三四郎に会うかもわからないのに、普段からあのハンカチ持ち歩かないよね?
そう思うと、“落ち着いていて乱暴”と称された美禰子さんも心に闇を抱えているのです。
激動の新しい時代の自立した女性。その葛藤が見て取れます。
そして物語を通じて三四郎は何か変わったか。否、きっと何も変わっていません。きっとこれからも。そこが三四郎の強さであり、美禰子が三四郎に惹かれた部分なのだと思います。
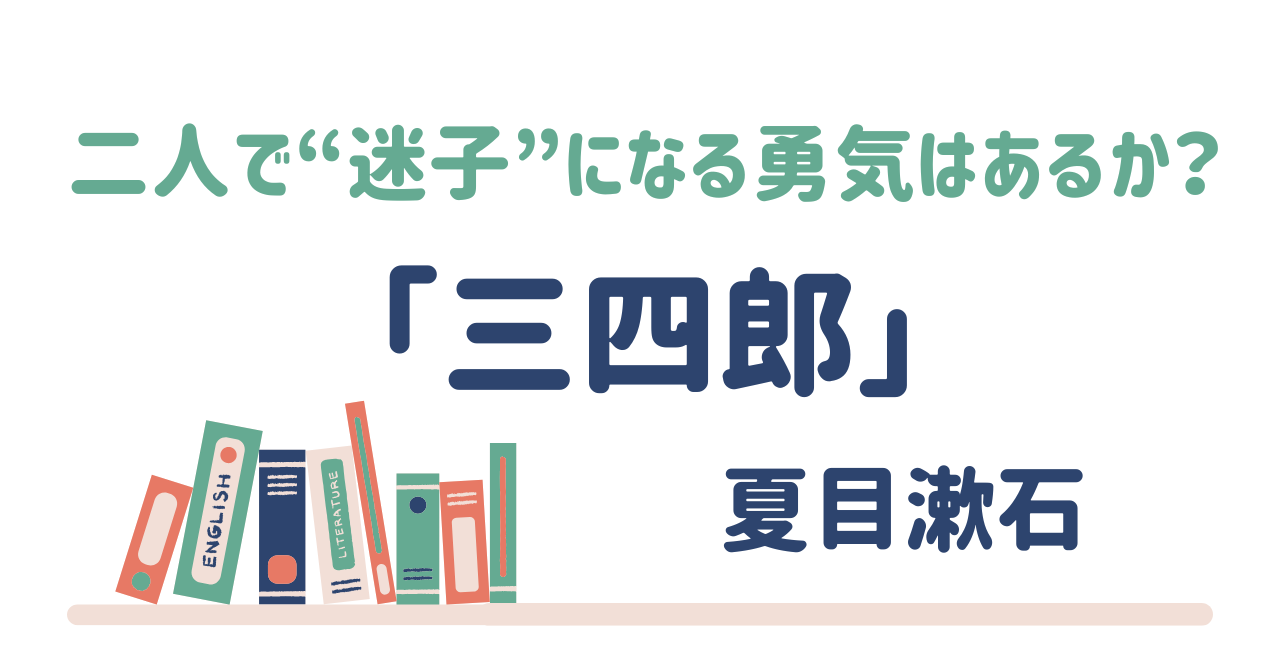

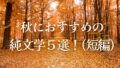
コメント