まるでガラス細工のような美しさと切なさ。「思春期の性」というテーマを扱っているにも関わらず、ここまで爽やかで清らかなのは堀辰雄ならでは。
透き通るような繊細な文章で紡がれる少年時代の淡い恋。
美しい少年に魅せられた、一人の少年の物語
主人公は十七の少年。親元を離れて寄宿舎がある男子校へ入ります。それまで親元で大切に育てられてきた少年が、男子ばかりのむさ苦しい空間に放り込まれ、そこでなんとかやっていこうと四苦八苦している様子が伺えます。部屋の匂いが夢にまで出てくる描写は、なんかリアルで笑ってしまいました。
性への戸惑いと嫌悪感
主人公は彼らの中では一番背が低く、髭もまだ生えていない、おそらく華奢な少年。そこでガタイの良い魚住という上級生に狙われます。思いっきり引いてしまう主人公(顔が青くなっています)。直前に描写のある「蜜蜂による花の受粉」と合わせて戸惑いと嫌悪感の表現が見事です。
美しく中性的な少年、三枝との出会い
主人公の住む部屋に、一つ年上の三枝という噂の美少年が転校してきます。三枝は白い肌が特徴的な中性的な少年。
風邪を引いたことをきっかけに、主人公と三枝との距離が少しずつ縮まっていきます。そしていつしかその関係は友情の限界を超えつつあるところまできます。
美しい中性的な少年に魅せられていく主人公。この辺りの描写は美しくキラキラしています。
魚住が、誰も何も言わなくても二人の関係にちゃんと気づいているところも良かったです。
夢から覚めるとき
夏休みに二人はある半島へ一週間の旅行に出かけます。どんよりとした天気と「いくぶん陰気になりながら」という描写に何か罪悪感のような、後ろめたい思いを抱いているのがわかります。
宿屋で、三枝の脊椎カリエスの痕についての二人のやりとりがあります。なんでしょう、この、見てはいけない美しいものを覗き見しているような感覚…いやらしさのない清らかさが見事です。
そして、乗合馬車に乗るために入った村で、とある娘たちに出会います。主人公はその中で目元の美しい少女が気にかかります。彼女の印象に残るために無理に話しかけて少し恥をかきます。その際に、意地悪そうに笑った三枝に一種の敵意を感じます。これが主人公にとってリアルな異性との出会いであり、「異性への目覚め」でした。
三枝はそれに嫉妬していたのでしょうか。明け方近く、目が覚めて見た三枝の背中とかすかな歯ぎしり。この描写になんとも切ない予感を感じます。
握った手。電車を降りて互いにその姿を探しても、一向に見えないままの別れ。
それを機に三枝とは疎遠になります。その間、脊椎カリエスを再発していた三枝は、秋の新学期が始まるとすでにどこかの海岸に転地。そして冬になり、主人公は掲示板で三枝の死を知ります。
最後の衝撃
数年後、主人公は肺結核のためある高原のサナトリウムに入ります。そこで三枝を連想させる十五、六の少年と出会います。
そしてある日、その少年が裸で日光浴をしているところを見かけます。少年は誰にも見られていないと思い自分の下半身を見つめています。目を細めてよく見ると、その背中に三枝と同じような脊椎カリエスの突起があるのを見つけます。それを見た主人公は激しく動揺します。立っていられないくらいの衝撃です。それから数日後、少年はそんな主人公の動揺には気が付かず、無事に退院していきます。
この描写が何を意味するのか。さまざまな解釈があると思います。そこがまた面白いところです。
三枝をそういった対象として見ていた過去の自分を突きつけられたから?それは後悔なのか?彼の中では単なる黒歴史だったのか?
そしてそれは「過去」なのか?という疑問があります。ここ数年でたくさんの少女と出会い楽しく恋愛してきたので、本人も“もう何ともない、忘れた”と思い込んでいただけなのでは。もしかして、少女たちとの恋に精神的な繋がりはさほどなかった…?
何年経とうが、誤魔化しようのない、逆らえない「三枝」という存在に衝撃を受けたのではと思いました。主人公の嗜好というより、“三枝”という存在が主人公にとって特別だったのではと思います。
本気の恋だったのではないでしょうか。それに気がついてしまったのではないかと思います。そうであったとしたら、何とも切ない。三枝はもういない。さよならもちゃんと言えていない。そしておそらく三枝も本気だった。
主人公が永久に失ったものは「燃ゆる頬」をした三枝だったのではないでしょうか。
最後の場面で、その現実を突きつけられたのだと思います。
読んだ本の中でもダントツと言っていいほどの「切なさ」
思春期という、不安定で精神的にも肉体的にも揺らぎの多い時期。感受性も高く、色んな刺激を素直に受け止める時期でもあります。
そんな少年から大人への過渡期に出会った美しい少年、三枝。彼の持つ儚く危なげな魅力と美しさに魅了された主人公。その夢のような出来事は、三枝が亡くなったことにより読者に強烈な切なさを刻みつけます。
今でも忘れられない一冊です。
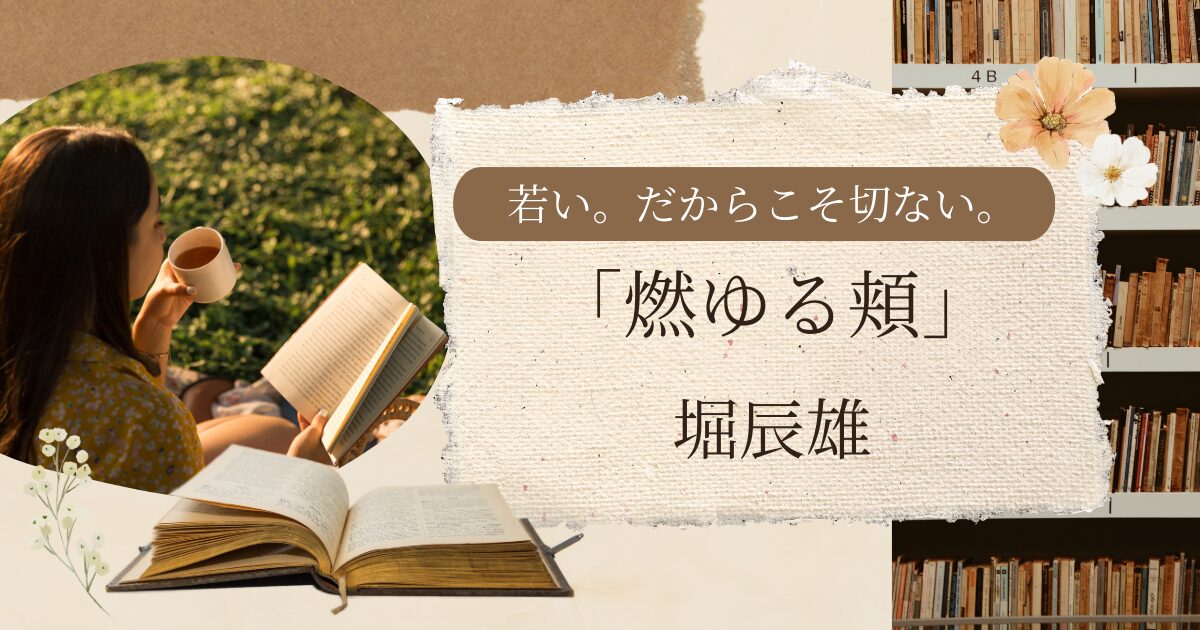


コメント